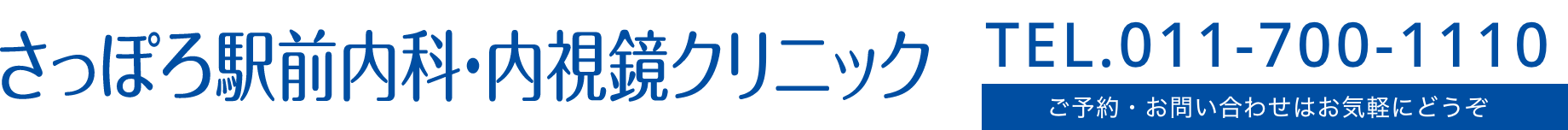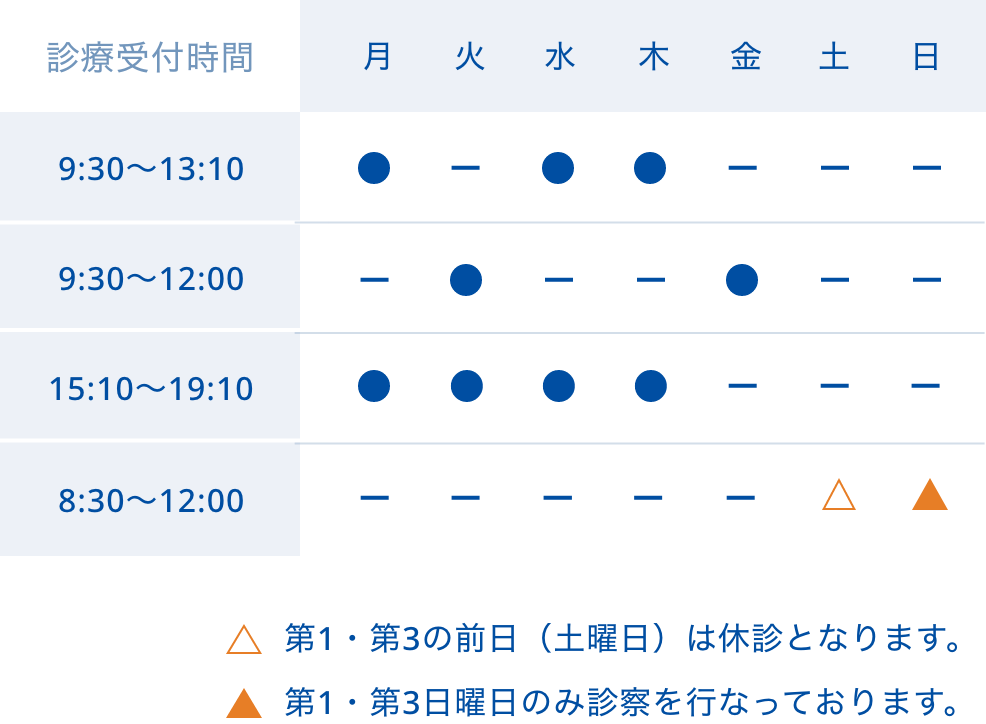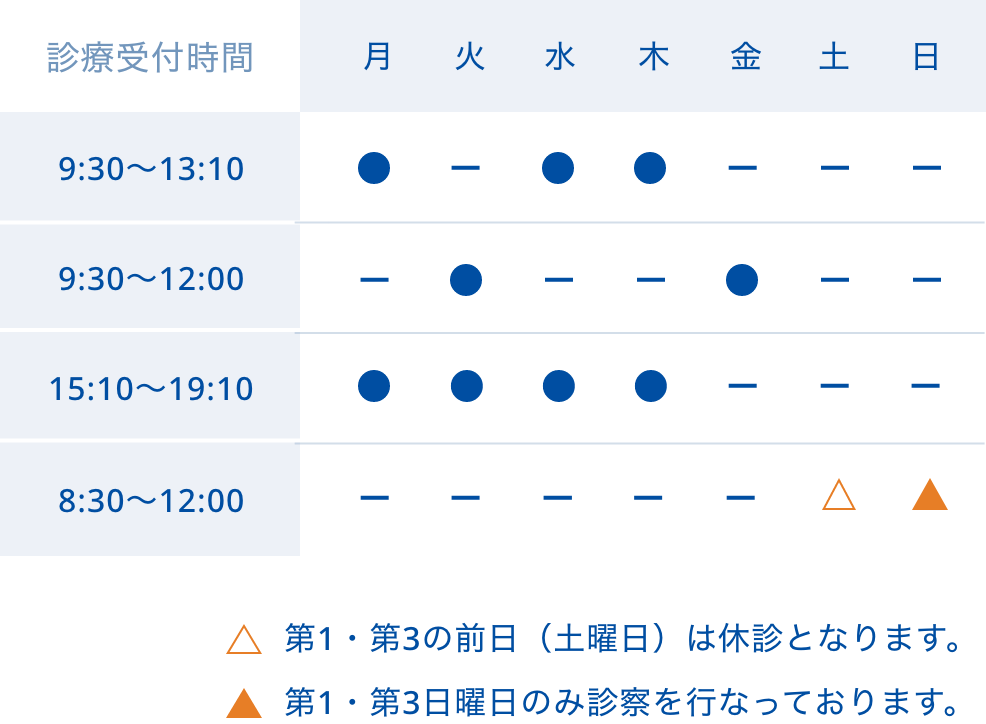


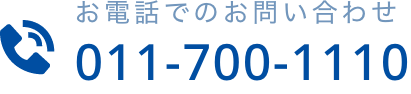

当院では内視鏡技術を磨き続けて20年以上の内視鏡医師が胃もたれの診断および検査を実施しております。患者様の状態にあわせて適切な胃もたれの治療方法をご提案させていただきます。
胃もたれ以外でも、胃カメラ検査・胃内視鏡検査・胸焼け・胃酸の逆流・胃がん・逆流性食道炎・胃潰瘍・ピロリ菌などでお悩みの方は札幌市北区にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックまでお気軽にご相談ください。
質問を押していただくと、その質問内容の回答が下に表示されます。
胃もたれとは、食後に胃のあたりが重く感じたり、消化が遅れているような不快感が続く状態を指します。
人によっては「胃の中に食べ物がずっと残っている感じ」「食べすぎたときのような圧迫感」「胃が膨れて張る感じ」と表現されることもあります。
一般的に、食後1〜2時間たっても胃がすっきりしない、むかむかするという症状を伴うことが多く、慢性化すると日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまいます。
そのため胃もたれに対する丁寧な診察と必要に応じた検査を行い、原因を見極めたうえで的確な治療を行う必要があります。
胃もたれの原因はさまざまですが、もっとも多いのは「胃の運動機能の低下」です。
食べ物が胃から腸へスムーズに送られないと、胃の中に内容物が停滞し、胃の膨満感や不快感が生じます。
これは加齢やストレス、暴飲暴食などでも起こります。また、脂肪分の多い食事やアルコール、冷たい飲み物は消化を妨げ、胃の動きを鈍らせる傾向があります。
さらに、胃炎や胃潰瘍、胃がん、膵臓や胆のうの病気が隠れていることもあるため、症状が続く場合には注意が必要です。
一時的な食べすぎによる胃の重さと、胃もたれは一見似ていますが、性質が異なります。
食べすぎの場合は、単純に食事量が多すぎたことで胃に物理的な負担がかかり、数時間で自然に解消されることがほとんどです。
一方、胃もたれはそれほど食べていなくても起こることがあり、「少ししか食べていないのに胃が重い」「何を食べてもすっきりしない」などの慢性的な症状を訴える方が多くいます。
こうした場合、胃の機能低下や慢性胃炎、消化不良、胃の病気などが隠れている可能性もあるため、単なる食べすぎとは区別して対応することが必要となります。
胃もたれが続く場合、まずは問診で症状の詳しい状況を確認します。その上で、必要に応じて「胃カメラ検査(上部消化管内視鏡)」を行うのが一般的です。
胃カメラでは胃の粘膜を直接観察し、慢性胃炎、胃潰瘍、ポリープ、がんなどの有無を確認できます。
加えて、ピロリ菌検査や超音波(エコー)検査、血液検査、消化管機能検査(消化速度の測定など)が実施される場合もございます。
病気の早期発見・早期治療のためにも、慢性的な胃もたれは放置せず相談しましょう。
胃もたれの治療は、原因に応じて薬物療法と生活習慣の改善を組み合わせて行われます。
薬としては、胃の運動を助ける「消化管運動促進薬」、胃酸の分泌を抑える「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」、胃粘膜を保護する「粘膜保護薬」などが使われます。
また、薬物療法だけではなく、脂っこい食事を避ける、よく噛んで食べる、食後にすぐ横にならない、食間を空けすぎないといった食生活の工夫も重要です。
慢性的な胃もたれには、ストレスとの関連もあるため、リラクゼーションや睡眠の質の改善も有効と言われています。
はい、胃もたれを引き起こしやすい食品には共通点があります。
たとえば、脂肪分が多い揚げ物や肉類、バター・クリームなどの乳脂肪製品は、胃での滞留時間が長く、消化に負担がかかります。
また、チョコレート、アルコール、カフェイン、炭酸飲料、香辛料などは、胃酸分泌を過剰に刺激したり、胃の動きを乱したりする原因になります。
冷たい飲み物や、消化に時間がかかる食物繊維の多い食材(生野菜、豆類など)も、胃もたれを誘発する場合があります。
機能性ディスペプシア(FD)は、胃もたれを代表的な症状とする消化機能の異常で、検査では目に見える異常がないにもかかわらず症状が続く病気です。
胃もたれの中には、このFDに分類されるケースが少なくありません。
FDには「食後愁訴症候群(PDS型)」と「心窩部痛症候群(EPS型)」の2タイプがあり、前者は主に胃もたれや早期満腹感が、後者は胃の痛みや焼けるような感覚が中心となります。
治療には、胃の運動を助ける薬や抗不安薬が用いられるほか、ストレス管理も大きなポイントとなります。
はい、胃もたれはストレスと密接に関連しています。
強いストレスや緊張、不安を感じていると、自律神経のバランスが崩れ、胃の運動機能や胃酸の分泌に異常をきたします。
その結果、食べ物の消化が遅れ、胃に負担がかかりやすくなります。
特に仕事や家庭のストレスを感じている方、睡眠不足の方、機能性ディスペプシアを併発している方は、ストレスによる胃もたれが悪化しやすい傾向にあります。
当院では、身体だけでなく心の状態にも目を向けた診療を行い、必要に応じて他科目の医療機関と連携しながら対応しています。
胃もたれの治療で使用される薬には比較的安全性が高いものが多いですが、副作用がゼロではありません。
たとえば、消化管運動促進薬は稀に不整脈や眠気を引き起こすことがあります。
また、PPIは長期服用によってミネラルの吸収障害や腸内環境の変化、感染症リスクが報告されています。漢方薬や制酸薬も、体質に合わないと下痢や腹部膨満感を起こすことがあります。
薬の種類によっては妊娠中や高齢者には慎重な投与が求められることもあるため、自己判断での服用は避けることが重要です。
胃もたれが数日で治まらず、何週間にもわたって続く場合は、自己対処ではなく医療機関の受診が必要です。
慢性的な胃もたれの背景には、胃炎や機能性ディスペプシア、ピロリ菌感染、消化器腫瘍などが潜んでいる可能性があります。
札幌市/札幌駅にある当院では、詳細な問診に加え、胃カメラ検査や血液検査、ピロリ菌検査などを組み合わせて、正確な診断を行っています。
再発を繰り返す胃もたれには、生活習慣の見直しや心理的ストレスのケアも欠かせません。症状の経過を記録しておくことも、適切な診断と治療につながりますので、お早めにご相談ください。
当院では内視鏡技術を磨き続けて20年以上の内視鏡医師が胃もたれの診断および検査を実施しております。患者様の状態にあわせて適切な胃もたれの治療方法をご提案させていただきます。
胃もたれ以外でも、胃カメラ検査・胃内視鏡検査・胸焼け・胃酸の逆流・胃がん・逆流性食道炎・胃潰瘍・ピロリ菌などでお悩みの方は札幌市北区にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックまでお気軽にご相談ください。